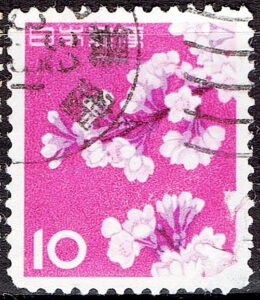引き続いて同様のキロボックスからの消印です。
ソメイヨシノ10円の昭和39年「西舞鶴局」の唐草和文機械印です。昭和30年代、唐草和文機械印は主にハガキ用として使用されていました。昭和36年郵政省に郵便機械企画室が設けられ、日本電気による書状用押印機の開発が始まりました。N1型機、N2型機、N3型機と試作されましたが実用に至りませんでした、その経緯は下記にまとめましたのでご参照ください。実際に書状押印機が使用されたのはN4型機で昭和41年に入ってからです。しかし、日本橋局やその他の局でも書状額面切手に昭和30年代の唐草和文機械印を見かけることから、他局でも押印されていた可能性があります。特に昭和38年3月頃に配備されたN1型試作機21局の消印がそれに当たるのではないかと思われます。その当たりの詳しい資料(配備局)がなく説明が出来ないのが残念です。今回の消印はハガキに10円切手を貼って押印されたのか、書状押印機が配備されて書状に押印されたのかはわかりません。
(書状用自動押印機配備の経緯)
・昭和36年12月頃=郵政省と日本電気の間で書状郵便物への機械引受押印機開発の研究が開始
・昭和36年5月頃=N1型試作機が東京中央局へ配備
・昭和38年3月頃=N1型試作機が全国主要21局へ22台を配備(日本橋局や岡山局など、配備局は不明)
・昭和39年3月頃=N2型試作機1台が東京中央羽田空港局(TOKYO INT)へ配備され、到着印として欧文活字を組み込んで使用(航空書状がサイズは整っているため)
・昭和39年3月=N3型機が東京中央局へ配備され実用化(しかし操作できる職員が1人だったため常時使用されず郵便物が多い時のみ使用)
・昭和40年=N4型機が正式採用され、東京中央局、豊島局、大阪中央局、京都中央局へ各1台配備(詳しい配備日時は不明)
・昭和41年=N4型機が東京、大阪方面の22局に28台配備(局名は不明)
・昭和42年=N4型改良機が全国各地の局へ64台配備